【先輩留学生の就活成功ストーリー】準備の仕方も目指すべきところも長期目線で

明治大学 商学・会計系専攻
チョウさん(2025年3月卒業)中国出身
【就活データ】
就活時期 :2022年12月~2024年6月
インターン :20社応募⇒12社参加
本エントリー:30社
面接参加 :16社
内定数 :8社
内定先 :総合商社
就活開始前から心構えの準備はできていた
私の就活スタートは2022年の12月、まだ大学2年生の冬。日本人と比べて日本の就活や日本での働き方に詳しくない。本選考の面接では自分のことをどう伝えるかが重要になるけど、日本語ネイティブの日本人でもこのコミュニケーションを失敗することがあるので、自分はもっと失敗する可能性がある。だから3年生になったら一気に就活を初めて行こうと思っていたんですが、だったら今から始めても良いんじゃないか?と思ったのがこのタイミングでした。
こうやって考えられたのは、大学1年生の時から学外の学生団体に所属したり、3~4年生向けのチームワークの授業に参加したりして、上級生と会話する機会が多かったことや、家業で日本企業の人と自分がやり取りしていたこともあって、就活を始めようって考える前から日本の就職活動に向けての心構えができていたからです。
心構えはできても、就活の進め方など具体的にはイメージできていませんでした。どのくらいエントリーしたら面接にはこのくらい進めるかなーとか、毎日ES書いて説明会参加して予定びっしり!見たいな事でもありません。まずは2年生だけど4年生向けの説明会に参加してみようという所からのスタートです。 
適性検査の対策を進めることで運の要素を減らしたい
就活で特に力を入れたのはSPIや玉手箱などの適性検査の対策です。面接まで進めれば勝つ自信はあったんですが、ESや適性検査はそこまでの自信がありませんでした。運の要素もあるので。でも、この運の要素を極力減らしたい。そのためには適性検査やるべきだと思って取り組みました。
適性検査は日本人の中学高校レベルの問題が結構多いんですが、日本の中高と中国の中高で学ぶ内容が違うので、日本人には当たり前でも自分にとっては馴染みのない問題もあります。特に、確立や計算問題が中国ではあまり触れなかった分野でした。対策方法としては、
・問題集をひたすら解いていく(10冊以上、各2~3周は実施)
・本番の適性検査を受ける(インターンシップの応募は適性検査の練習にもなる)
という感じでした。
この対策の通算期間は約1年くらいだけど、1日20分~30分くらいという日が多くて、本番のテスト直前には2~3時間くらい集中してやるという感じですね。
SPIは問題の形式が多い(確率、推論、速度算、割合など)ので色々できるようにならないといけません。
玉手箱は割とシンプル(図表、読み取りなど)な問題が多いので慣れればスピードで溶けるようになっていきますよ! 
やるべき準備は多いからこそ同時進行で進めていく
適性検査の対策をしっかりやったおかげもあり、志望度が高い企業の7割は面接まで進むことができました。でも準備をすればいいのは適性検査だけじゃありません。
今就活の1年半を振返ってももうやりたくないって思うくらいやること多すぎて大変でした(笑)ESで落とされたり、面接官との会話が盛り上がらず落ちたりってたくさんありました。でも、それは次の成功に繋がるチャンスだと思って取り組んでください!1人で悩んで抱え込まず、大学の先生や就活仲間に頼ってください!事前準備してきたことが、本選考の時に全部繋がります。どれだけ地道な努力をしてきたかが結果になります。そしてどんな結果になったとしても就活はゴールではないので、長期的な目線を持って就職活動頑張ってください!
▼GlobalLeaderより
チョウさんはインタビューの中でも向上心や好奇心をって行動できる人だと感じさせる部分が沢山ありました。そして、それを感じられたのは就活テクニックではなく、基礎になる考え方や心構えがしっかりできているからだという事も感じました。社会人になっても基礎を大切にし大きな成果を成し遂げてください! 
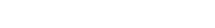 グローバル人材と企業をつなぐジョブサイト
グローバル人材と企業をつなぐジョブサイト